こんにちは!今日は多くの方が気になっている「介護認定」について詳しく解説していきたいと思います。家族の介護が必要になったとき、「どこから始めればいいの?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
介護認定とは?
介護認定とは、介護保険サービスを利用するために必要な手続きです。要介護状態や要支援状態にあることを公的に認定してもらうことで、様々な介護サービスを1~3割の自己負担で利用できるようになります。
申請できる人は?
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 40歳~64歳で特定疾病のある方(第2号被保険者)
特定疾病には、がん(末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、認知症などが含まれます。
申請の流れ – ステップバイステップ
STEP 1:申請書類の準備
必要な書類を準備しましょう:
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 医師の意見書(後日医師が直接市区町村に提出)
- マイナンバーカードまたは身元確認書類
STEP 2:市区町村の窓口で申請
お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で申請します。地域包括支援センターでも代理申請が可能です。申請は本人以外にも、家族や居宅介護支援事業者、地域包括支援センターの職員が代行できます。
STEP 3:認定調査
申請から約1週間後に、市区町村の職員や委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)が自宅や施設を訪問して認定調査を行います。
調査内容:
- 身体機能・起居動作(立ち上がり、歩行など)
- 生活機能(食事、入浴、排泄など)
- 認知機能(記憶、理解など)
- 精神・行動障害(昼夜逆転、徘徊など)
- 社会生活への適応
STEP 4:主治医意見書の作成
かかりつけ医に意見書を作成してもらいます。心身の状況、医学的管理の必要性などが記載されます。
STEP 5:介護認定審査会での審査
認定調査結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で審査されます。
STEP 6:認定結果の通知
申請から約30日以内に結果が通知されます。認定は以下の7段階に分かれます:
- 非該当(自立)
- 要支援1・2
- 要介護1~5
認定後にできること
要支援1・2の場合
- 介護予防サービス(介護予防訪問介護、介護予防通所介護など)
- 地域密着型介護予防サービス
要介護1~5の場合
- 居宅サービス(訪問介護、通所介護、短期入所など)
- 施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など)
- 地域密着型サービス
申請時のポイント・注意点
調査日の準備
- 普段の状況を正確に伝える:「今日は調子がいい」ではなく、日常の困りごとを伝えましょう
- 家族が同席する:本人が遠慮がちに答える場合があるので、家族のサポートが大切
- 具体的なエピソードを用意:「時々転ぶ」ではなく「週に2回は転倒している」など
よくある失敗例
- 本人が見栄を張って「大丈夫」と答えてしまう
- 調査当日だけ頑張ってしまう
- 家族が代わりに手伝いすぎて実際の能力より高く評価される
認定に納得できない場合
結果に不服がある場合は、都道府県の介護保険審査会に不服申立てができます。また、区分変更申請や状況が変わった時の更新申請も可能です。
費用について
- 申請料:無料
- 認定調査:無料
- 主治医意見書:無料(市区町村が医療機関に支払います)
まとめ
介護認定の申請は思っているより複雑ではありませんが、正確な情報提供が重要です。遠慮せずに普段の困りごとを伝え、必要なサポートを受けることで、本人も家族も安心して生活できるようになります。
不明な点があれば、お住まいの地域包括支援センターや市区町村の介護保険担当窓口に相談してみてくださいね。一人で悩まず、専門家の力を借りながら進めていくことが大切です。
この記事が皆さんのお役に立てれば嬉しいです。介護は家族みんなで支えていくものです。制度をうまく活用して、無理のない介護生活を送ってくださいね。

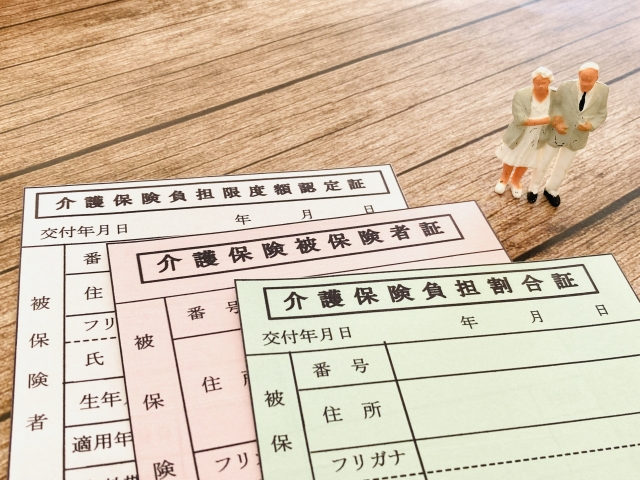


コメント